 トップページへ戻る
トップページへ戻る| 1.学校紹介 | 2.本事業の計画 | 3.取組みの概要 | 4.実施状況 | 5.まとめ |
5.まとめ
|
平成19年度学校自己評価によるアンケート結果について |
(1)授業・授業改善について
| 教職員 H17 H18 H19 | 生徒 H17 H18 H19 | 保護者 H17 H18 H19 | |
質 問 内 容 |
研修・公開授業・授業評価・ 他校訪問等により,教職員の 授業改善・意識向上が図れた。 項目なし 2.8 3.2 |
わかりやすい授業が多い。 2.6 2.6 2.8 |
勝山高校の授業については信 頼しており安心して任せること ができる。 (各教科についての意見を 自由記述) 質問内容変更 3.4 3.4 |
| アクティブハイスクールの指定を受けてさまざまな授業改善につながる方策を実行してきたが,その成果が次のグラフAに現れている。 授業改善が図れたという教員が昨年度9%だったのが今年度33%まで劇的に増加している。教員は他校訪問をし,その道で有名な,スキルの高い先生の生の授業を見学し,年に2回の「授業公開」で切磋琢磨し,年2回の「生徒による授業評価」で生徒の評価にさらされ,否が応でも自分自身の授業のあり方について考え,授業改善が行われたと思われる。 その結果,生徒の「わかりやすい授業が多い」という質問への評価が,平成18年度から平成19年度にかけて2.6から2.8へと0.2ポイントも上昇している。 ただし,上昇したといってもまだ2.8であり,少なくとも3.0を超えるような評価点になるように努力を重ねていかなければならない。 |
 |
(2)学力伸長について
| 教職員 H17 H18 H19 | 生徒 H17 H18 H19 | 保護者 H17 H18 H19 | |
質 問 内 容 |
生徒の実態を踏まえて,学習 指導の徹底や工夫をしている。 3.4 3.6 3.5 |
学校の課題や宿題は,量や質 が適切で家庭学習がしやすい。 2.5 2.6 2.7 |
勝山高校は生徒の学力を伸ばす ように努力している。 質問内容変更 3.6 3.6 |
| 前出(1)で教員の授業改善の意識は上がり,上の表でも教員自身,学習指導についての徹底・工夫の評価点は平成19年度も3.5と高い。 生徒は課題や宿題の量は適切だという評価は上昇しているが,進路指導課が行う学習実態調査によれば,家庭学習時間が増加しているとはいえないことを考えると,評価が上昇していることにも一考の余地がある。 上記の質問に対する保護者の評価点は3.6という高さからも窺えるように信頼は厚く,それに応えるべく,これからも努力しなければならない。 |
(3)勝山高校で学ぶことへの満足度
| 教職員 H17 H18 H19 | 生徒 H17 H18 H19 | 保護者 H17 H18 H19 | |
| 質問内容 | 生徒や保護者の満足度を高める ような指導内容と方法について 工夫をしている。 3.3 3.4 3.4 |
勝山高校で学ぶことに満足して いる。 2.9 3.0 3.3 |
子どもを勝山高校で学ばせることに 満足感を持っている。 質問内容変更 3.7 3.8 |
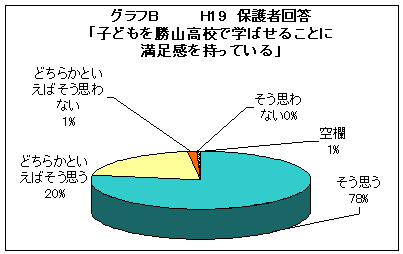 |
生徒の評価点が平成18年度から平成19年度にかけて0.3ポイントも上昇しているのは,部活動・学園祭等の学校行事の充実による満足度もあるであろうが,教員の学習指導の内容と方法の工夫も一因であろう。 保護者欄の3.8という数字は驚異的とも思える評価だ。グラフBを見てもらえばわかるが,「そう思う」と回答した保護者が約8割である。 否定的な評価は1%にすぎず,ありがたい評価であり,今後気を引き締めてこの評価に違わぬような指導をしていかなければならない。 |
| (3)来年度にむけて 学力向上拠点形成事業とアクティブハイスクール事業の指定を受け,校内でさまざまな取り組みをしてきたが,多忙感が増したことは否めない。 しかし,次ページ掲載の平成19年度学校自己評価のアンケート結果の保護者による評価点が非常に高く,また昨年度と比較しても,生徒からの評価が上がっており,頑張ってきた甲斐があったと思う。 ただ,この信頼を裏切らぬように,これからも特に授業改善につながる仕掛けを考えていきたい。 |
本年度のアクティブハイスク-ル支援事業の事業計画で設定した数値目標は次の(1)~(5)である。
アクティブハイスク-ル支援事業プロジェクトチ-ムでこれまでの本校の進路実績及び本年度3年生の進路希望,活動実績,学力等を分析し年度当初,設定したものである。また一部,学校経営計画ともリンクしている。
| (1)国公立大学合格者 → 60名以上 (2)東京・京都大学合格者 → 1名以上 (3)商業科国公立大学合格者 → 1名以上 (4)就職率(地元就職率) → 100%(50%以上) (5)卒業生進路希望実現満足度アンケート → 80%以上 |
(1)国公立大学合格者 → 60名以上 について
国公立大学合格者数(含む既卒生)過年度比較 (H20.3.24現在)
入試種別 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 AO入試 CTなし 0 3 2 1 CTあり 0 1 4 0 推薦入試 CTなし 6 6 6 13 CTあり 9 11 4 8 小 計 15 21 16 22 一般入試 前期 28 30 24 34 中期 0 2 1 5 後期 8 8 6 1 小 計 36 40 31 40 合 計 51 61 47 62
| 本年度の特徴としてAO・推薦入試の合格者が過去最高の22名(これまでは平成17年 度の21名が最高)であった。特にセンター試験を利用しない入試で14名の合格を勝ち取
った。これまでセンター試験を利用する入試で数をだしている傾向があったが新たな展開と なった。本年度の3年生は1~2年次の総合的な学習の時間等を活用し,町おこしや真庭バイオマスタウン構想に関する学習といった地域連携を意欲的に取り組んできた学年である。 その経験が面接や小論文で生かせたのが大きな成果に結びついた要因であると考えている。 本校のAO・推薦入試に関する進路指導体制の一つのスタイルが確立されてきたと思う。 一般入試では理系はセンター試験で実力を発揮し順当に得点し,合格者も現時点で31名となっている。一方,文系はセンター試験で理数系教科でおもうように得点できず2次出願も志 望変更せざるを得ない生徒が多数にのぼった。またセンター得点での業者判定がA~Bで前 期合格を見込んでいたにもかかわらず2次試験で逆転され不合格となった生徒も例年に比べ 若干多いように思う。 現在,文系からは22名の合格者がでている。特に文系の指導につい ては充分な検証をし来年度以降に結びつけていく必要がある。 |
(2)東京・京都大学合格者 → 1名以上 について
| 理系生徒の中に1名京都大学の志望者がいた。薬学部を志望していたが理系科目の2次力に不安があり,薬学部はかなり厳しく医-保健・検査技術に志 望変更するようすすめた。結局,迷った末,第2志望の広島大学の薬学部を受験することに
なった。 京都大学は3年次になってから教員の薦めで志望してきたが,最後の局面で志望校 変更となった。よく言われることであるが,難関大志望者が自然発生的に存在するものではなく1年次から育てていく(つくりだしていく)ものであることを痛感させられた。 従来, 本校には難関大に対する指導方法は勿論,教員の中に難関大を薦めていく意識も低かったと思う。しかし昨年度からはじまった学力向上拠点形成事業や本事業に取り組む中で着実に本校からも毎年,難関大合格者を育てていこうという気運が教員の中に生まれてきたことは 「(2)東京・京都大学合格者→1名以上」という数値目標は達成できなかったがこの目標 を設定したことは大いに意義のあることだと考えている。 今後は五校交流会で話題となった難関大学指導についてなんらかの企画を立ち上げていきたいと考えている。 |
(3)商業科国公立大学合格者 → 1名以上 について
| 商業科生徒から和歌山大学観光学部への合格者がだせた。 本年度3年生は1年次から町 おこしや真庭バイオマスタウン構想とリンクし地域連携に意欲的に取組んできた学年であった。 そういった取組を通して培った知識やコミュニケーション能力,プレゼンテーショ ン能力を活かして「町おこし」をテーマにして受験(志望理由書・面接)し合格を勝ち取った。 本校の商業科の目玉である地域連携で学んだことを,進路決定にどう結びつけていくか一つのスタイルが確立してきたと考えている。 今後は毎年,国公立大学への合格者を育てることで教員の指導の感覚・ノウハウを引き継いでいくことが重要であると考えている。 |
(4)就職率(地元就職率) → 100%(50%以上) について
| 就職希望者普通科3名,商業科17名,合計20名全員の就職が決定し就職率100%を達成している。 また、地元就職者は12名で地元就職率60%で数値目標の50%以上も達成している。 地元事業所からも本校に対する人材供給への期待は大きく来年度以降も,事業所見学や社会人活用講座,勝高プロジェクトK-仕事の達人講座等を通して地元貢献 への意識を育てていきたいと考えている。 |
(5)卒業生進路希望実現満足度アンケート → 80%以上 について
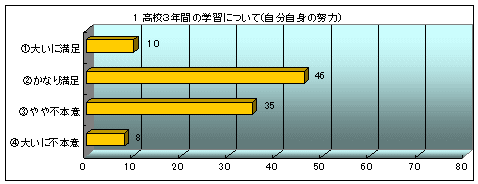 |
| 43%の生徒が「やや不本意・大いに不本意」と答えている。 3年間の努力を振り返った時 3年次の努力から比べると1・2年次に「もっと努力できたのでは」と思うのではないだろうか。本校の置かれた地理的な環境から周囲にライバル校や予備校もなく,また大学生等に出会うこともないので1・2年次はのんびりとした高校生活を送ってしまう。 3年次の後半になり推薦入試等を受験してみて初めて受験というものを知るのである。と同時に1・2年次如何にのんびりとした生活をおくっていたのか痛切に感じるのではないだろうか。 本校の1・2年次の大きな課題ともいえる。 |
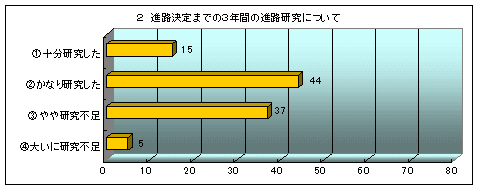 |
| 42%の生徒が「やや研究不足・大いに研究不足」と答えている。質問1とよく似た結果となっている。 進路研究することと学習することは比例することがみてとれる。意欲の源となる進路研究を充実させていかなくては意欲的な学習につながらない。 進路研究の大切さがあらわれている。 |
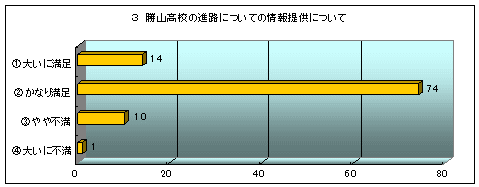 |
| 88%の生徒が「大いに満足・かなり満足」と答えており,本校の進路の情報提供についてまずまずの評価が得られている。一方で11%の生徒が「やや不満・大いに不満」と答えている。 その理由に国公立大学指向に偏重しているとの指摘があった。生徒・保護者・地域が本校に期待する進路指導の第一に国公立大学への進路保障があり,その点を踏まえた上で私大等を志望する生徒への的確な情報提供が必要である。周囲に予備校等がないため学校の進路指導に頼らざるを得ない状況にあるだけに本校の果たすべき責任は大きい。 生徒・保護者から高い満足度が得られるよう先を見通した的確な情報を提供したいと考えている。また商業科の生徒では「やや不満・大いに不満」と答えた生徒は皆無であった。 |
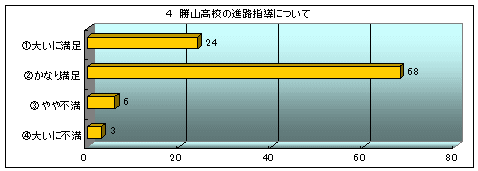 |
| 92%の生徒が「大いに満足・かなり満足」と答えており,本校の進路指導について高い評価が得られていると考えている。 一方で9%の生徒が「やや不満・大いに不満」と答えている。 その理由に質問3と同様に国公立大学指向に偏重しているとの指摘があった。本校の使命の第一が国公立大学への進路保障であることを認識し,1・2年次の進路に対する考え方をしっかり伝えておくことが大切である。 その上で私立大学志望者にも的確な指導をしていく必要がある。また商業科の生徒には「やや不満・大いに不満」と答えた生徒は皆無であった。 |
 |
| 87%の生徒が「大いに満足・かなり満足」と答えている。まずまずの評価が得られていると考えている。 「大いに満足」と答えた生徒の中には,第一志望でなくとも本人が全力で受験に取組み合格を勝ち取った生徒が多い。 一方「やや不満・大いに不満」と答えた生徒は13%である。その多くが1・2年次の授業内容が十分理解されていなく,3年次の授業にも十分集中できていない。また受験に際しても「やりつくした」感が十分もてなかった生徒が多い。 結局,生徒が満足できるかどうかは第一志望でなくとも本人が「やりつくした」感がもてるかどうかであると思う。最後まで頑張らせる・あきらめさせない指導が必要である。 |
進路指導課が実施している学習実態調査2年生1月のグラフである。
|
||||
|
||||
| 2年生で学習時間が平日平均100分,休日平均123分というのは,本校の目標である平日平均が180分,休日平均300分に対しかなり少ない。 細かく分析していくと平日は概ね時間割に沿って学習しているようである。つまり数学であれば90分-0分-90分というように翌日,数学の授業があれば前日に学習するが,なければしないというスタイルであり毎日一 定時間学習はしていないようである。 時間割に関係なく学習時間の固定化が必要であると考えている。また休日については平日に対して学習時間は微増するだけである。周囲に競う他校の生徒や塾,予備校も少なく学習に対する刺激は極めて少ない。 都市部の生徒であれば塾や予備校等に通い学習時間を確保するであろうが,本校生徒はグラフからわかる通り休日も平日と同 じペ-スで学習しているようである。週末課題の質・量の再検討及び休日の使い方について指導が必要であると考えている。 我々教員も教員集団として学習時間を確保させようと指導する意識が低いとも言える。まずは学習実態調査の期間だけでも意識して学習時間の確保を強く生徒にせまるといった姿勢が必要であると考えている。 1,2年次のこの,のんびりしたところが本校の大きな課題である。 |
||||
アクティブハイスク-ル支援事業に取り組んでみて |
||||
| 本事業に取り組んでみて最も良かった点は「とにかく結果はともあれやってみよう」という気運が教員の中に生まれ学校が活性化されはじめたことだと思う。 五校交流会やバイオマス利活用シンポジウム,1・2年生合同発表会などがその良い取組事例である。学校が比較的落ち着き実績や成果が出せている時,「前年度の通りにすればいいのではないか」と考えがちである が,その考えこそが学校の発展を停滞させ,学校・生徒・教職員の元気を奪っていく原因であると思う。 次に従来,本校は課主導ではなく学年団主導の色合いの強い学校であった。そのため学年団によって指導方針や指導体制が大きく異なり,進路実績等にもバラツキが生まれ安定 感に欠けるところがあった。しかし本年度は,本事業が三学年に対して一本の柱となり学年団 連携が構築されてきたと思う。さらに普通科と商業科といった学科併設校での科目標の違いか ら起こる温度差といったものが本事業が緩衝剤となり逆に学科併設校であることのメリットが 引き出せてきたことは大きな成果であったと思う。 またこれまでも商業科を中心として地域連携はしてきたが,本事業を通して普通科を巻き込んでの地域連携をより深化させることができたことも大きな成果であった。以前の一学年6クラス体制から現在の4クラス体制となり,全学年でも12クラスのこじんまりとした学校となった今,生徒数は480名,教員数は30名余りである。 だからこそ逆に学年団や学科にとらわれることなく生徒及び教職員が全校体制で学校活性化に取り組んでいく意識をもつことが,こじんまりとした学校ならではの独自性や優位性を引き出すことにつながっていくと考えている。 |
||||
|
|
||||